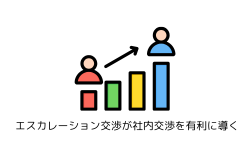施設基準と課内環境
施設基準の上位取得を積極的に目指す病院は目指すし、結局目指さない病院はとことん目指さない。この施設基準を満たしていると思われるのでと提案しても、テコでも動かない課長もいる。結局のところ、施設基準の届出は病院としての気持ちだとの精神論に達する。
届出をしない病院は、要件を満たさない要因を一生懸命に探している状況すらある。これでは一生、届けられない。
解釈が微妙なところは国の発した難解な文章であるので存在するし、補足するためにも疑義解釈という事務連絡が出る。
充分に事務連絡は網羅されていないので、その範囲は基準を満たさないということが明らかになるまでの間は届出を行って良いと言うことになる。もちろん、明確に満たさないと記載されているものを除いて。
消極的な病院はこの時点で尻込みするし、わからないから届出しない、と言う驚きの論理になる。または、厚生局に解釈を尋ねるのだが「◯◯管理料について当院は⚫️⚫️で☆☆なので、基準を満たさないですよね?」という尋ね方をする。
人間誰だってこのように尋ねられたら、基準を満たさないことを説明できないか、と厚生局側も考えるようになる。
これでは、もはや届出をしようとしているのか、していないのかがわからない。
施設基準の上位取得は精神論、と言ったのはここに起因する。前向きな気持ちで届出を行えば問題にならないし、このように厚生局に聞いても回答の結果は変わってくる。
医事課長が、施設基準の届出が病院の経営に強く関与しているんだという意識が希薄だと言ったらそれまでだが、医事課内でなぜ施設基準がもう少し取れないのかと言う声が上がってこないのかも不思議だ。課長が取ろうとしないとその文化も蔓延する。医事課は特に、どこの病院でも上の雰囲気が影響を与えることが多い部署だと思う。
長年勤めたキャリアのある人、リーダーシップのある人、プレイヤーに徹している人、あまり無関心な人。そしていわゆるお局、と呼ばれる方々。
見事にその空気が施設基準の届出にも反映されていると思う。経営者は医事課の風通しの良さに気を配る必要がある。
施設基準だけでなく、返戻査定対応についてもそうだ。課長の取り組みが浸透するだけでなく、お局が管理する伝統工芸品が医事課内を席巻する。
また、思い込みが算定ミスや未届出に繋がるケースもあるのでやはり第三者が定期的に確認をする必要がある。
また、これらの管理は医事課長自体の評価に繋がるのだろうが、公立病院などでは人事考課に項目が入っておらず責任感がないケースも見受けられる。
施設基準を見れば、だいたいの医事課像は透けて見えてくる。役職者の経営感覚は施設基準と切り離せない。なかなかこのような教育体制にまで病院のなかで配慮できているところも少ないように思う。
民間病院と公立病院の差が開くのもこの感覚の違いはあるだろう。医事課というお財布のがま口を大きくしておくか、非常に重要な観点だ。