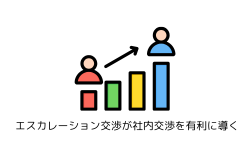届出受理後の措置等
タイトルがなんのこっちゃ、、という感じだが、病院の施設基準において人員数や夜勤時間数が満たさないときの変動ルールというのがある。それが、「届出受理後の措置等」にあたる。これを正しく認識している人が意外に少ない。月単位の入院料にかかわるルールなので、非常に重要だ。
例えば、平均在院日数や月平均夜勤時間数であれば、「暦月で3か月を超えない範囲の1割以内の変動」、7対1などの看護師配置であれば「暦月で1か月を超えない範囲の1割以内の変動」が許容されるということだ。
月平均夜勤時間数であれば、72時間以内であることが求められるが、「暦月で3か月を超えない」とあるので、1割以内、すなわち79.2時間までであれば、3か月連続までは続いて良いことになる。4か月目に、72〜79.2時間であった場合は3か月を超えてしまうので施設基準の変更届出が必要になる。
ここでひとつポイントなのは、4か月目が重要であるということ、そして3か月連続のうちに一度でも1割以上、80時間などを記録してしまうとその時点で、施設基準の変更届出が必要になる点だ。
逆に、一度でも72時間以内に収まれば、その時点で当然連続記録はリセットされる。ふたつめのポイントは4.5.6月が72.3、75.8、78.3と72時間を上回ってしまい1割以内であった場合、届出を行うのは7月頭ではなく、8月頭であるという点だ。一ヵ月の届出準備期間がある。
もちろん、この7月に72時間以内を満たせば暦月で3か月を超えないので取り消し、逆転が可能だ。対策としては、7月に何とかモニターをすれば、クリアすることができる。
このことを知らず、夜勤時間で3月の時点、人員でその月を満たさなかったので即取り下げする例を見てきた。看過してしまったことが恥ずかしく悔やまれるほどだが、こういうことがある。
近年は夜勤看護師の確保をすることが難しく、どの病院でも満たすことが難しくなってきている。しかし、その夜勤時間数の計算は様式9を以て行われるが、この様式9が正確なルールで作られているかがかなり怪しい。
30病院ほどの様式9を定期的に見る機会があるが、看護部で作るケースと医事課で作るケースがあるうえ、看護部長(室)の人員もわりと頻繁に代わることもあるせいか、正確な様式9の作成方法が引き継がれない傾向にある。
結果、夜勤時間数が多くなりすぎていたり、申し送りの設定がもったいなかったりする。
また、当該月で16時間(急性期病棟の場合)以上勤務した看護師の数が月平均夜勤時間数の計算の分母になるが、シフトで工夫する最善の努力を先ほどの切羽詰まった1か月に行っているかなど見直す必要がある。
そのため様式9は非常に重要な書類だ。
まして入院基本料に関する要件なのでとても大事なのだが、意外に盲点である届出受理後の措置、と様式9。教科書にはあまりフォーカスされないが大事な話。あくまで実務上、大切なことはフォーカスしたい。
やはり基本は大切、、、。