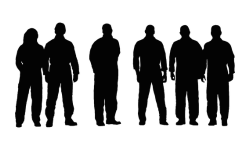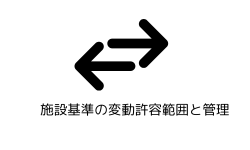見積もりの取り方
委託契約や購入など各取引先からの見積もりを得る時にやってはいけないこと。
・PDFの見積をもらうこと
・入札でないのに入札書式の再利用
・1社だけの見積もりをもらう
・取引先の見積もりフォーマットで指定なしにもらう
・他の種類の契約の見積書の再利用
結論からすると、すべて適切でない見積もりの取り方だと考えている。入札の場合は話が変わって来るが、競争環境の働く随意契約ではきちんと各社を比較することが必要だ。
比較の対象は当然、同業他社のサービスに加えて当該社の過去の提案もあるということを忘れてはならない。
仕様書ばかりに注力されて見積書の作成が、おざなりになっているケースが良くある。
先方の定めた見積書では毎年変わったり、必要な情報を得ることができない。
見積書は本来、病院で指定して各社とも同じ見積書雛形で提出してもらうことによって比較もしやすくなるし、他社の相違点が明らかになる。
委託契約では、管理費⚫️円、食材料費⚫️円いくらという見積書もある。
これでは、人件費が上がっているのかコメの値段が上がっているのか、まったく窺い知ることができない。
委託契約で言えば、この業務の人工は年間何日の何人で、人件費の人工単価は⚫️円で、管理費の%、業務管理費(利益)の%を聞くことで初めて他社との違いを把握できるほか、工数を聞くことで質の把握にも役立てることができる。
要は、できる限り細かい業務に細分化し、その業務がいくらで積み重ねがいくらでということが把握できる必要がある。
これにより他社だけでなく、過去の比較とも行うことができ、過去受けたデータは過去の産物でなく、生き返り意味のあるデータとなる。取引先が提出しているのは、今回だけの提案でない。過去からの提案すべてが、その企業の見積もりだ。
人工単価が上がっていれば、その都道府県の最低賃金の上昇率と比較してどうなのか比較ができる。
値上げが多いご時世だが、適正な値上げ幅なのか検証する必要があるが、項目が細分化されていなければ確認のすべがない。
また設備委託、清掃委託、警備委託などについては、国土交通省が毎年、国の建築物の保全業務を委託する際の労務単価の参考価格が公表されている。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001723888.pdf
これによって、今回の提案がどの位置にあるのかベンチマークをすることができるし、先方の提案が妥当であるのか把握することができる。
交渉は、客観的なデータに基づいた指摘は先方の社内でもわかりやすい指標になる。
また、病院のなかの稟議においても説得力の向上に寄与することは間違いない。
当然エクセルで作っているので他社と共通雛形であれば横に情報を付与して、一目でマスタの作成を行うことができる。
見積書はできる限り細かく、基本は毎年同じように、ということが必要だと考えている。