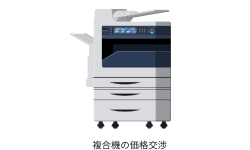交渉目標値の設定
価格交渉や見積合わせの中で、意外に忘れそうなのが交渉目標値の設定だ。
各社に見積を提出させて、一番安価な会社を中心に交渉してゆけばよいと短絡的に考えがちだが、これでは本当によい値を得ることができない。交渉の機会は1年に1回、よもや2〜3年に1回と限定されてしまうにもかかわらず、ベストな値を引き出すことができないのは、とても勿体無い。
判断基準として、価格はもちろん、実績や製品のクオリティなどいろいろな採用基準があるだろうが、この病院経営が厳しいご時世において、価格が決定要因の大きなウェイトを占めるのは間違いないだろう。
ケースによっては、メーカーなどからどれくらいがぶっちゃけ、目標値でしょうか?と尋ねられることがある。
この質問は取組のスキームを成功に導くか、相手の考えを探る意味でも重要な質問となる。
重要な駆け引きになる。
先方の会社のなかでの社内交渉でドライブを駆けることになるか否かの起点となるからだ。
見積依頼者は予め総取引額を把握して、どれくらいまで数量が伸びる予測があり、どれくらいの価格を下げたいのか、最高いくら、最低限いくらほどの価格は持っておくべぎだ。
かつて、まだ手をつけていない金額の高い領域において、勝負をかけてくるという文脈があるなかでの交渉において、総額の1/3ほどの価格ダウンを求めて、先方が提示する条件があるもののその価格を飲んでもらったことがある。
先方が10年契約という長い期間での提示という見返り条件があったものの、これはやはり取引だ。
取引には当然こちらの求める目標金額が必要となる。
それなのに、目標金額を考慮せず、漠然と交渉しているケースもよく見られる。
目標金額の設定によって、その交渉を何度まで繰り返すかということ、そして、本来は「妥結」の判断基準になるはずだ。どうも病院業界では、何回の交渉とか、いつまで交渉をしたとかで無意識にそれが妥結の判断基準となっていることが多いようだ。
目標金額の設定に至らなかったのはなぜなのか、目標金額の設定は適切だったのかを検証する必要がある。
競争が働く環境下で、こういった取引、交渉をすることが大事であり、その商材のシェアや全国におけるシェアの把握も重要になる。
まず、目標金額が常軌を逸したと思えるほど高く置いて良いケースなのか、現実的な目標をおくべきなのか。
読み間違えると、何も分かっていないとメーカーや代理店から呆れられるだけだ。
目標金額がメーカーや代理店にとって「リアル」な数値として受け止められると、社内交渉をこれぐらい頑張らなければならないとなる。背伸びしてできるかな、かなり高い厳しい目標だなと思ってもらうのが理想的なラインだ。
あー、それなら自分の権限で決裁できるな、楽勝!と捉えられてしまうと、見積もりは翌日に出すか、寝かせて見積提出期限の直前に出すだろう。
よって目標金額の探るのも見積もり依頼者の重要な仕事だ。
ただ見積もり依頼をメールで送り、リモート会議だけでやり取りしているとこのような結果を出すという点で質が落ちるように思える。勝負どころではお互い直接対面をして腹の探り合いをするというのが、良い交渉方法だと考えている。
交渉を繰り返していると、つい機械的な依頼になりがちであるが、小さな交渉ごとでも目標設定値、具体的な数字を用意しておくことが必要だ。先方も、こちらの本気を確かめようとしている。
目標値の設定は何を目指すにしても重要ですが、我々の医療業界の交渉においても大事です。