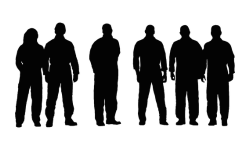デッドヒート理論
価格交渉する上で、やはり重要になるのが複数社間で「デッドヒート」する環境を作ることだ。A社に負けまいとB社が再提出、負けまいとA社が提出、それを上回ろうとB社が提出、、という状況だ。この状況は相手の社内決裁もおりやすく、何より価格を下げるためには担当者に社内で汗をかいてもらわねばならない。その状況をデッドヒートが産み出す、ということが大切だ。
受ける担当者も何度も何度も正確な比較に資料管理に追われて大変で、駆け引きに巻き込まれて精神的な疲労にも塞悩まされるが、対価としては大きなコスト削減を生む。
さらに何回か交渉が進めばおおごとになり、両社とも上席の担当者が同行するようになる。これも大切な要素だ。
今、提案を受ける側になってもそうだし、かつて旅行会社時代に形のない旅行という商材を取り扱っていたときも、某大手旅行会社とのデッドヒートは何度も何度も経験した。
駆け引きについては清廉潔白、担当者としては両社との信頼関係が重要であるので、もちろん、相手の価格を自ら伝えたり、匂わすのは御法度だろう。ここは営業マンの腕の見せどころでもあるが、上手なヒアリングしてくれれば情報を持っている側で伝えられる情報は伝えようと考えている。むしろ、場合によってはデッドヒートでなくても良いのだが、最終的に価格が下げられれば良いのだ。
もちろん自社のシェアの中から、「本命」、こちらに頑張って欲しいという思惑はあるだろう。その後の運用のことを考えれば明らかに楽。ということがあればそれは立派な選定要因だ。 しかし、本命以外にももちろん絞り込んでいないというスタンスを貫き、変わらず良い提案をし続けてもらう必要がある。
この緊張感という場の提供、創作は担当者の演技力、腕の見せどころだ。デッドヒートをけしかけるわけではないが、その競争環境が大事なもので今後の企業の行方を占う、その価格交渉の成功か失敗かを占うものになる。
内部の決定プロセスや検討状況を伝えることは、先方の提案修正に繋がるので大きなプラスになる。また、スキームに穴がないか、稟議の場での想定問答を尋ねることができるなどデッドヒートしている途中に、大事な着眼点が漏れていないか点検、確認の時間に充てることができる。同じ商材を扱う複数社が同じ指摘をしていれば、どこかに問題があると考えて見直すべきだろう。デッドヒートの渦中の時間にもメリットがあり、その提案は洗練されていく。
担当者との人間関係についても、上手く誠心誠意付き合うことでお互いの性格や考え方も理解できるようになってきて、今後の人間関係の構築にも役立つ。実際、方針を定めたあと、オペレーションをしてゆく際に人間関係の構築は大きい。
ややもすると避けがちな、デッドヒートだが結果的に有効になる。実現にはABC分析でやはりシェアの大きいもの、お互いに取って命運を握る大きなターゲットの際に起こる。そして二大巨頭のシェアがあり一般的にライバル関係とされる企業間で起こる。やはり、取扱額の大きいものから費用削減に取り組むべき、とする理由はここにもある。
成果を大きく出す交渉には、デッドヒートは外すことのできないひとつの大きな仕掛けだと思う。